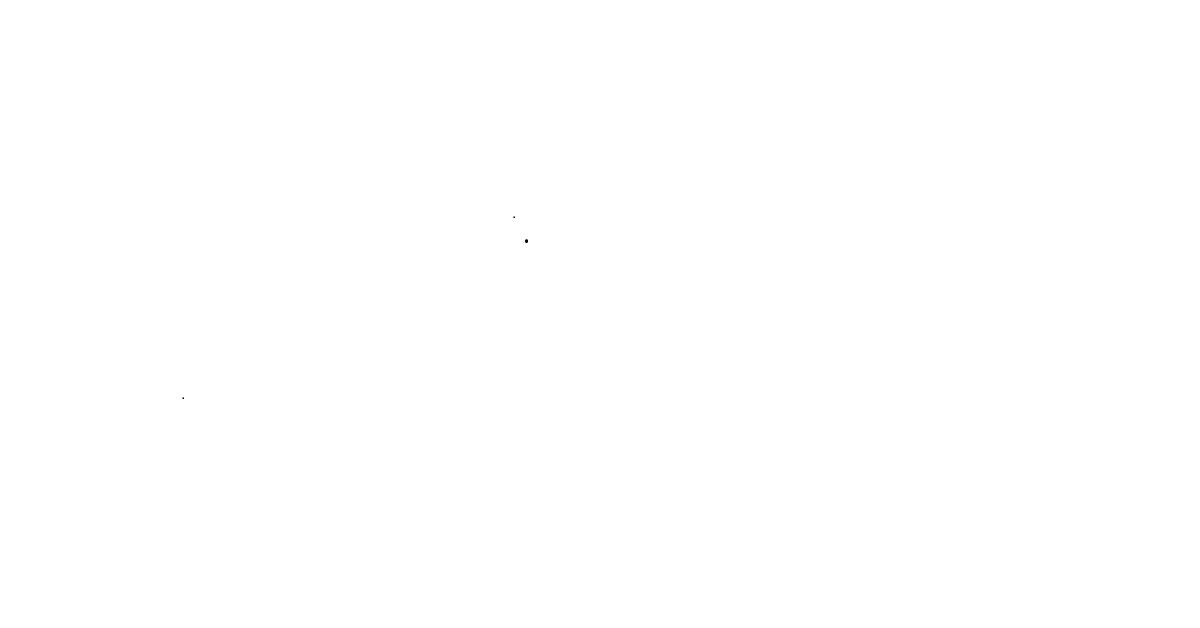YouTubeで活動するNEXT-GOさんが投稿した動画「【本音】障害者は子供を作るな!!」は、非常に議論を呼ぶテーマですが、その背景には彼自身の特異な体験があります。この動画は、一般的にほとんど語られることのない「子ども目線」からの現実を描き出しており、福祉や障害者支援の議論に新たな視点をもたらしています。
両親が知的障害を持つ中での成長
NEXT-GOさんの両親は、母親が軽度の知的障害、父親が複雑な知的障害を持っていました。母親は日常生活を送ることが可能で、現在は一人暮らしをしながら仕事もしていますが、父親はグループホームに入居しています。
幼少期、NEXT-GOさんは父親の存在を知らず、生まれてからすぐ乳児院に入り、18歳で児童養護施設を卒業するまで母親のみと関わって生活していました。父親の存在を知ったのは、役所の支援によりDNA検査で確認された後です。
この環境で育った彼の体験は、一般的な障害者支援や育児の議論とは一線を画します。「両親が障害者」という事実は、単なる家族構成の問題ではなく、子どもが日々直面する精神的負担や葛藤に直結しています。
子ども目線でのリアルな体験
NEXT-GOさんは小学生の頃、母親が週に一度施設に訪れ、おもちゃやお菓子を持ってきてくれることがあったものの、複雑な感情から無視していたと語ります。
成人後、社会での経験を通じて両親を理解し、許せるようになったといいますが、子ども時代は非常に繊細で、日常生活の中で精神的な負担を抱えて過ごしていました。
さらに、障害者の親が子どもを育てる際の現実についても独自の視点で話をしています。
NEXT-GOさんは、知的障害者と身体障害者の親を比較し、知的障害の親の場合、子どもが早い段階で親の知能を超えてしまうことがあり、精神的負担が大きくなると指摘しています。これは、障害者支援の議論ではほとんど触れられない重要な現実です。
大人目線では見えない子どもの苦しみ
YouTubeなどでよく見られる障害者の子育て動画は、ほとんどが大人目線で作られています。「福祉があるから大丈夫」「障害があってもやる気があれば大丈夫」といったメッセージは、親や支援者にとっては希望的な内容ですが、子ども自身には直接関係ありません。
NEXT-GOさんは、この大人目線の一方的な語りに疑問を抱き、子ども目線での体験を代弁するためにこの動画を制作しました。
子どもにとって、親が障害者であるという現実は逃れられず、日常生活の中で直接的に経験するものです。学校や周囲の子どもたちから「お前の親は障害者だ」という言葉を投げかけられることもあります。
成人してからは社会の多様性を理解し、過去の苦しみを受け入れることができるようになりますが、子ども時代にはその現実に押し潰されることもあります。
「覚悟」を問うNEXT-GOさんのメッセージ
動画内でNEXT-GOさんは、障害を持つ親が子どもを育てる場合、本当に成人まで育てる覚悟があるのかを問います。
これは単なる極端な主張ではなく、子ども目線から見た現実的な問いです。福祉や支援は確かに重要ですが、それがあっても子どもにとっての体験や精神的影響は変わらないことを強調しています。
この問いかけは、障害者が子どもを持つ権利や自由を否定するものではありません。むしろ、社会全体が「子ども目線のリアル」を理解した上で、支援や制度のあり方を再考するきっかけとなるものです。
子ども目線の議論の重要性
NEXT-GOさんの動画が貴重なのは、障害者の子育てを語る際に「子ども目線」を前面に出している点です。
福祉や支援の有無だけで語られがちな現実を、実体験を通じて明らかにすることで、視聴者に新たな気づきを提供しています。
子ども時代の精神的負担や葛藤、家庭内での役割の変化、大人になっても影響を受け続ける感情など、従来の議論では見落とされがちな視点を話しています。
また、障害者の病状や程度による違いも明示されており、知的障害者と身体障害者の親の違いや、知的障害を持つ親を持つ子どもが直面する独特の困難を具体的に示しています。この具体性が、動画を単なる意見表明ではなく、貴重な社会的資料として位置づけています。
まとめ
NEXT-GOさんの動画「【本音】障害者は子供を作るな!!」は、議論を呼ぶタイトルとは裏腹に、非常に深い洞察を提供しています。
両親が障害者である子どもの立場から語られる内容は、福祉や支援の現状を考える上で重要な視点です。障害者の親を持つ子どもが直面する現実、精神的負担、そして社会との接点における葛藤を理解することで、私たちはより建設的で現実的な支援や議論を構築できるでしょう。
この動画は、障害者支援や子どもの権利を考える上で、貴重な「子ども目線の声」を社会に届ける役割を果たしています。NEXT-GOさんが自らの体験を公開したことにより、従来の大人目線だけの議論では見えなかった現実が、多くの人々に届くことになったのです。