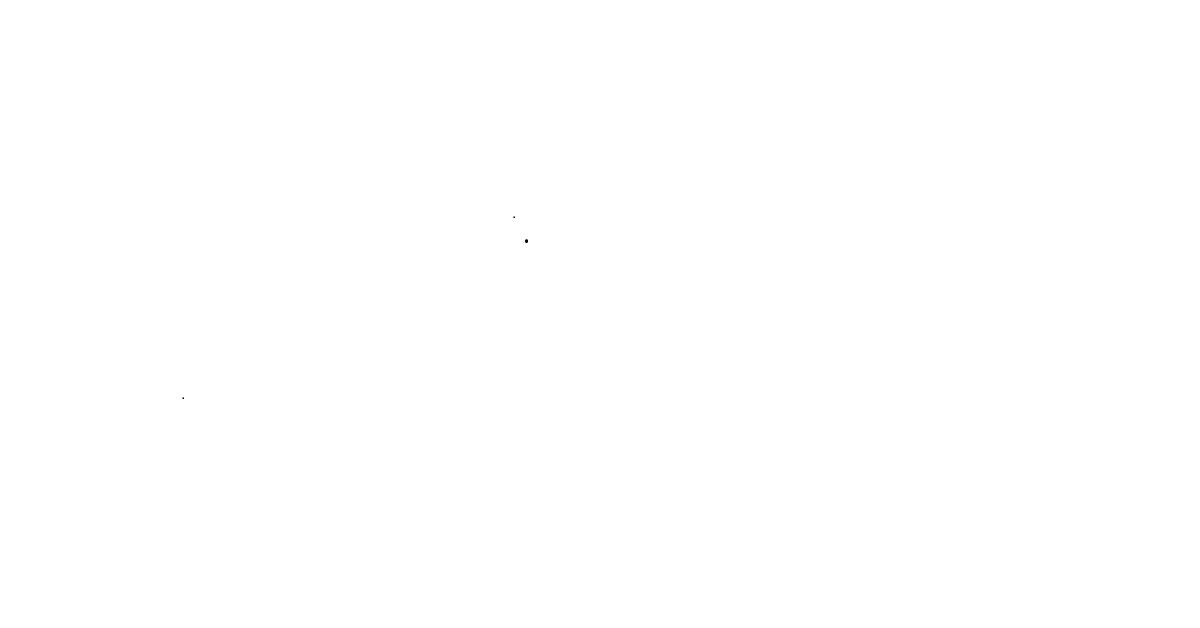私の祖母は、戦争の最中を生き抜いた女学生だった。
昭和5年生まれ。
10代の頃、彼女は国家総動員令のもと、ある「任務」に就かされた。
それが、風船爆弾の製造だった――。
国家に動員された少女たち
終戦間近、日本本土決戦に備える体制の中で、多くの女学生が学業を中断させられ、軍需に動員された。
祖母もその一人だった。
祖母が携わったのは「風船爆弾」と呼ばれる兵器。
和紙とこんにゃく糊で丁寧に組み立てられた巨大な風船に爆弾を吊り下げ、偏西風に乗せて太平洋を越え、アメリカ本土を狙うという、今思えばあまりに無謀で、しかし当時は国家の期待を背負った兵器だった。
もちろん、アメリカ本土へ届くことはなかった。
風船爆弾の製造には、器用な手作業が必要だったこともあり、若くて従順な女学生たちが動員されたという背景がある。
私の祖母の場合は風船製作に携わっていたのではなく、事務仕事を手伝っていたらしい。
特攻隊員を見送った記憶
祖母が何度か口にした記憶がある。
それは、特攻隊員たちの出撃を見送った日のことだった。
飛行場の近くに動員されていたこともあり、彼らが飛び立つ日、少女たちも整列して見送りをしたという。
まだ10代後半の少年たちが、
「行ってきます」と笑いながら機体に乗り込み、
空へ消えていく。
それを見送る女学生たちも、まだ少女だった。
祖母は、「あの時は涙が止まらなかった」と言っていた。
どの顔も、もう二度と戻ってこないことを皆が知っていた。
でも、その場で止めることは誰にもできなかった。
特攻隊に選ばれた人たちは、先鋭部隊だったため、当時はまぶしく見えたらしい。
だったため、当時はまぶしく見えたらしい。
いい人たちだったと言ってた。